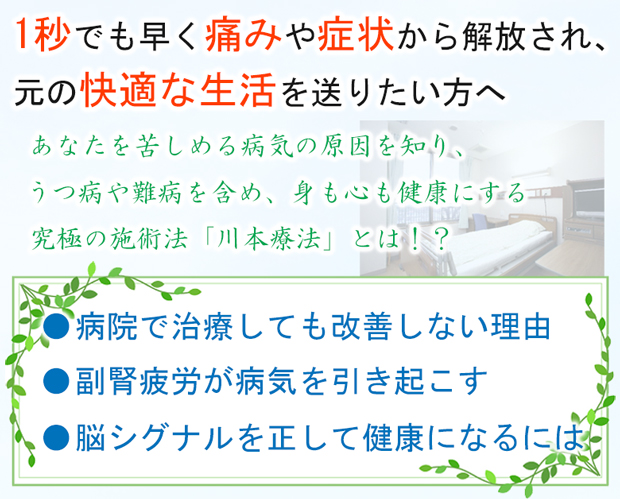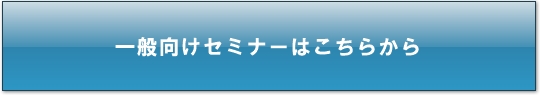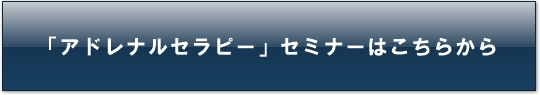低エネルギー状態と副腎疲労との関係
低血糖症ではなく「低エネルギー症」である
唐突ですが、低血糖症はなぜ起きるのでしょうか? ここで、低血糖症状について解説していきます。
「血液中に糖(グルコース)が多い状態」を高血糖状態といいます。一方、「血液中に糖(グルコース)が少なくなった状態」を低血糖状態といいます。血液中の糖はグルコースを測定しています。
低血糖症とは、高血糖状態から急激に低血糖症になった「落差」(血液に糖=グルコースが少なくなった)で、手足の震え・思考力の低下・疲労感など体調の不調が発生すると教えられてきました。
しかし、考えてみると不思議ではありませんか? 高血糖状態から低血糖状態になったということは、糖は細胞内に運ばれたと推測できます。
細胞内に糖が運ばれたなら、細胞のミトコンドリアは糖を代謝してエネルギーを生産することで、人は元気になるはずです。
しかし、低血糖時には手の震えや思考力の低下などの症状がでます。不思議ですね。
糖の行方
血液中の糖(グルコース)が減る=低血糖状態。それでは、血液中から減った糖(グルコース)はどこに運ばれたのかと考えてしいまいます。
人のエネルギー源は糖質です。(特に脳) 血液中の糖が減ったということは、その糖はどこに運ばれたのでしょうか? 一般的に考えられのは「細胞に運ばれた」と推測できます。
上記で、細胞に糖(グルコース)が運ばれたなら、糖(グルコース)は細胞でエネルギーに変換され、「元気」になるはずということはお伝えしました。
しかし、低血糖の時は、手足の震え・思考力の低下・強い疲労感がでます。ここが不思議な点です。
糖(グルコース)が血液中から減るルートは2つあります。それをまとめてみます。
①糖はインスリンホルモンの作用で、細胞内に運ばれる
②インスリンホルモンに対し細胞膜のセンサー(糖鎖)が受け入れを拒否し、細胞膜外に一時的に存在する
「②」の場合の糖は中性脂肪化して皮下に溜まるか、再度血液中に戻される(異論がある人もいます)
このページでは、「①」の細胞内に運ばれた糖の行方について述べていきます。
細胞内に糖(グルコース)が達しているにもかかわらず、低血糖症状(手の震え・思考力の低下)が起きるのはなぜでしょうか?
それは、糖(グルコース)が細胞内に到達したとしても、エネルギーに変換されていない状態と推測できます。
糖質には種類がある
ここで、重要なことをお伝えします。糖質についてのおさらいです。
ブドウ糖(グルコース)はご飯、パン、めん類などが胃腸で分解されてできた糖です。
一般的に「砂糖あるいはショ糖(サクロース)」といわれているのは、ブドウ糖(グルコース)単体で構成されているのではありません。
・砂糖(サクロース)は「糖(グルコース)+果糖(フルクトース)」から構成されています。
果物・蜂蜜も砂糖と同じ「糖(グルコース)+果糖(フルクトース)」です。
上記したように糖質には種類があることを理解してください。
さらに、憶えて頂きたいことは「代謝が悪くなった」ということを良く耳にしますが、その代謝が悪くなるというのは「糖代謝」が悪くなったということです。
糖代謝(エネルギーに変換される)されやすい糖・されにくい糖がある
上記したように、砂糖や蜂蜜や黒糖(砂糖)は「糖(グルコース)+果糖(フルクトース)」です。これらが細胞に到達すると速やかにエネルギーに転換されます。つまり、糖代謝が活発になるということです。
一方、ご飯やパンめん類などが消化されできる糖(グルコース)は細胞内に到達してもエネルギーに変換されにくい糖です。
したがって、グルコースが高血糖状態から低血糖になった=細胞内にグルコースが運ばれたとしても、エネルギーに変換されにくいことで疲労感が出るなど、いわゆる「低エネルギー状態」になるのです。
つまり、グルコース(ご飯やパンめん類などが消化されできる糖)では細胞内ではエネルギーに変換されにくい糖質であるということです。
さらに、グルコース(ご飯やパンめん類などが消化されできる糖)に植物油脂(ココナツオイル以外)が結合することで、細胞内でもエネルギーに変換効率は低下します。
例えば、うどんよりパスタを食べた後の方が低エネルギー状態は強く発症し、またご飯よりカレーライスを食べたほうが低エネルギー状態を強く発症することは皆さんも経験されていると思います。
なぜなら、パスタやカレーライスはグルコースに植物油脂が結合しているからです。
低エネルギー状態は生命危機である
人にとって、低エネルギーの時は生命危機状態といえます。なぜなら、その時に獣(けもの)に襲われても何も抵抗できないからです。
したがって、人には低エネルギー状態を回避するために様々な機能が備わっています。
その一つが副腎で生産されるホルモンです。人が低エネルギー状態になると、その危機状態が視床下部へ伝わり、視床下部から下垂体に命令がくだされます。
視床下部から命令を受けた下垂体は、副腎に対しホルモンを生産するように指示します。下垂体から命令を受けた副腎は血糖値を上昇させるホルモンを生産します。
日ごろから低エネルギー状態を感じている人は、そのたびに視床下部→下垂体→副腎ルートが作動し、副腎で生命危機を脱するためのホルモンが生産されています。
副腎疲労症候群という病気が現代病の1つにあります。副腎疲労症候群とは字のごとく、副腎が働き過ぎて疲弊することが発症原因になり、自己免疫疾患を患ったり様々な症状を発症します。
副腎ホルモンはストレス対応ホルモンです。現代社会はストレスが多く、副腎でホルモンを生産する回数もとても多くなっています。さらに、糖がうまく代謝できないで発症する「低エネルギー状態」時も副腎ホルモンは生産されてしまうことで、副腎はさらに疲弊します。
糖を摂取しても低エネルギーにならない人も多くいます。一方、1日に何回も低エネルギー状態に陥る人もいます。後者のようなタイプの人に対し、低エネルギー状態が起きにく体にしていくのはどのしたらよいかがとても重要です。
なぜなら、低エネルギー状態が起きるたびに副腎がホルモンを生産し疲弊してしまうからです。
参考文献 糖尿病は砂糖で治す 崎谷博征著
川本療法の神髄を伝授:無料メルマガ登録
低エネルギー状態と副腎疲労との関係 関連ページ
- ストレスと副腎の関係
- 副腎と脳の関係を理解する
- 皮膚と脳と副腎との関係を理解する
- 視床下部と下垂体と副腎の関係
- 副腎ホルモンの重要性
- ホルモン量が正常でも症状が回復しない理由
- ホルモンが造られ過ぎても、体調不良が起こる
- 副腎疲労症候群の原因と病態
- 虐待と副腎と免疫の関係
- 副腎疲労症候群になりやすい性格や環境
- 細胞が生産する物質と副腎疲労の関係
- 副腎を医学界が認識しない理由
- 低血糖ではなく、「低エネルギー症」である<
- 体内で「糖を生産する」ことが下手な人がいる
- 副腎疲労症候群に糖質ゼロ甘味料は禁止である
- 副腎疲労症候群と塩分と果物の関係
- 副腎疲労症候群にビタミンCの落とし穴
- 副腎疲労症候群とアレルギー疾患の関係
- 「5月と腰痛と副腎の関係」
- 低気圧で体調が崩れる理由
- アナフェラキシーショックの真実
- 副腎疲労症候群と慢性の炎症体質
- 副腎疲労症候群と自己免疫疾患の関係
- 副腎疲労症候群と甲状腺の関係
- 副腎疲労症候群と女性ホルモンの関係
- 副腎疲労と甲状腺と更年期の関係
- 「副腎疲労と過度な運動がしたくなる人」の関係
- 「怒り」と副腎疲労症候群の関係
- 副腎疲労症候群と糖尿病の関係
- 起立性調節障害の発症理由:「免疫が過剰なタイプ」
- 起立性調節障害の原因:活性酸素と電子チャージについて
- 起立性調節障害の発症理由:「感覚器官が過敏なタイプ」
- 3つある「エネルギー源」が弱い:消化器管が弱いタイプ
- 3つある「エネルギー源」が弱い:糖質を代謝できない
- 起立性調節障害が発症しやすい学年
- 起立性調節障害が5月に発症しやすい理由
- ヘルペスウイルスで原因不明の神経痛や頭痛を生じる理由
- 突発性難聴はヘルペスウイルスに侵されて生じる
- ヘルペスウイルスで生じる群発性頭痛、筋線維痛症、多発性硬化症
- ヘルペスウイルスで生じるベーチェット病や全身性エリトマトーデス
- 自律神経失調やうつ症状をひも解く